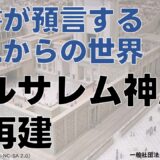「どうして、たった三つのことを信じるだけで人は救われるのか?」
これが「福音の三要素」の教えを聞いた人の率直な反応かもしれません。そのため、福音の三要素を信じれば救われる」と言うと、「本当にそう言い切れるのか」という疑問を投げかけられることや、「福音の三要素だけでは救われない」と反論されることがあります。
救いの教理は、永遠に過ごす場所を決定付ける大事な教えです。また、信仰生活の上にも大きな影響を及ぼします。そのため、少しくどいと思われるところもあるかも知れませんが、この記事では「なぜ福音の三要素を信じることで人は救われるのか」を詳しく解説したいと思います。
> 福音の三要素とは福音の三要素とは
福音の三要素とは、1コリント15:3~5に記されている以下の3つの教えで、この3つを信じるなら救われるというものです。
- キリストは私たちの罪のために死なれた
- キリストは死んで墓に葬られた
- キリストは三日目によみがえられた
新約聖書では、この3つが救いに最低限必要な信仰の内容として教えられています。
> 福音の三要素で救われる理由福音の三要素で救われる理由
「なぜ福音の三要素で救われると言うことができるのか」という疑問に対する答えを一言で言うと、「新約聖書で使徒パウロがそう語っているから」ということになります。
聖書に記された使徒パウロのことば
福音の三要素が記されている1コリント15:1~5では、次のように言われています。
1 兄弟たち。私があなたがたに宣べ伝えた福音を、改めて知らせます。あなたがたはその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。 2 私がどのようなことばで福音を伝えたか、あなたがたがしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなたがたが信じたことは無駄になってしまいます。
3 私があなたがたに最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、 4 また、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおりに、三日目によみがえられたこと、 5 また、ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
ここで注目してほしいのは、パウロは1節で「私があなたがたに宣べ伝えた福音を、改めて知らせます」と語り、2節で「この福音によって救われます」と明言していることです。そして、3~4節で、福音の内容として福音の三要素を語っています。つまり、(1)キリストは、聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、 (2)葬られたこと、(3)聖書に書いてあるとおりに、三日目によみがえられたことです。
あなたが聖書を神のことばとして信じているなら、以上が福音の三要素を信じることで救われると信じるに足る証拠となります。もし「三要素を信じるだけでは足りない」と主張されるなら、聖書に記された使徒パウロの言葉を否定するあなたは何者ですか、ということになります。
新約聖書には、パウロがそのように断言できた理由も書かれています。ガラテヤ1:11~12で、パウロは次のように語っています。
11 兄弟たち、私はあなたがたに明らかにしておきたいのです。私が宣べ伝えた福音は、人間によるものではありません。 12 私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。
ここでパウロは、自分の語っている福音は、イエス・キリストから直接啓示されたものであることを明かしています。そのため、パウロは「この福音によって救われます」と明言することができたのです。
よくある誤解
よく誤解されることなので申し上げておきますが、パウロは福音の三要素が福音のすべてであると語っているわけではありません。それは「私があなたがたに最も大切なこととして伝えたのは」(1コリント15:3)という言葉からわかります。つまり、重要性としては劣るかもしれないが、福音には福音の三要素以外の要素もあることを示しています。たとえば、携挙の教えも福音に含まれると思います。しかし、携挙を信じているかどうかは、福音の三要素のように救いに必須の条件ではないということです。
また、福音の三要素を信じるには、「キリスト」とは誰かということを知っている必要があります。また、「罪」とは何かを知っておく必要があります。そういう意味では、聖書のほかの箇所が語っていることも知っている必要があることになります。
しかし、そのような用語を理解した上で、福音の三要素を信じていれば救いを受ける条件を満たしているというのが、1コリント15:2でパウロが語っていることです。
旧約聖書の証言
福音の三要素を記した1コリント15:3~4では、「聖書に書いてあるとおりに」と二度も言われています。これは「聖書で預言されているとおりに」という意味です。ここでいう「聖書」とは旧約聖書のことです1。旧約聖書に記された「メシア預言」と呼ばれる預言どおりに、キリストは人の罪のために死なれ、墓に葬られ、復活されました。福音の三要素がメシア預言の成就であることも、パウロが語る福音はそのまま受け入れるに値するものであることを裏付けています。
また、福音の三要素に関するメシア預言の成就については、記事「聖書が語る『福音』とは?」をご覧ください。
以上で、福音の三要素で救われる理由を述べました。聖書を字義通りに受け取れば、以上の説明で十分だと思います。ただ、以上の説明では納得しない方もおられると思いますので、以下ではよくある疑問にお答えしたいと思います。
> よくある疑問よくある疑問
「ケファに現れ、それから十二弟子に現れたこと」はなぜ福音の要素に含まれないのですか?
福音の三要素が記されている1コリント15:3~5では、次のように書かれています。
3 私があなたがたに最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは、聖書に書いてあるとおりに、私たちの罪のために死なれたこと、 4 また、葬られたこと、また、聖書に書いてあるとおりに、三日目によみがえられたこと、 5 また、ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
3節の「キリストは」で始まる文は、5節の「ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです」で終わっています。この5節が福音の要素に含まれないのはなぜか、という疑問を持つ方がいます。本来なら、福音の「三要素」ではなく「四要素」ではないかという疑問です。
また、1コリント15章でパウロが語る福音の記述は、4節で終わっているのではなく、11節まで続いているとし、以下の9つすべてが福音の要素となるはずだと主張する方もいます。
- キリストが私たちの罪のために死んだこと。
- 葬られたこと。
- 三日目によみがえったこと。
- ケパ(ペテロ)に現れたこと。
- 十二人に現れたこと。
- 五百人以上の兄弟たちに同時に現れたこと。
- ヤコブに現れたこと。
- すべての使徒たちに現れたこと。
- 最後にパウロに現れたこと。
ただ、4~9節はすべて「キリストが弟子たちに現れたこと」と要約できます。そのため、以下では「なぜキリストが弟子たちに現れたことが福音の要素に含まれないのか」という質問に置き換えてお答えします。
1コリント15:3~5に記されている福音の要素は、よく読むと次のような構造になっていることがわかります。
- キリストは私たちの罪のために死なれた(要素1)
- 要素1を裏付ける事実:キリストは墓に葬られた(要素2)
- キリストは三日目によみがえられた(要素3)
- 要素3を裏付ける事実:キリストが弟子たちに現れた
キリストが墓に葬られたという記述は、キリストが死なれたことを裏付ける事実として提示され、キリストが弟子たちに現れたという記述は、キリストがよみがえられたことを裏付ける事実として提示されています。
このように見ると、キリストが弟子たちに現れたという記述は、独立した要素ではなく、キリストが復活したという要素3を裏付ける事実となります。つまり、「キリストは三日目によみがえられた」という要素の一部と考えることができるということです。
ただ、ここで湧き上がってくる疑問点があります。一方の「キリストは墓に葬られた」という事実は、なぜ独立した要素として、福音の三要素に含まれているのかということです。この疑問については、次の質問でお答えします。
なぜ「墓に葬られた」という要素が必要なのですか?
正直に言うと、私もかつては「福音の三要素ではなく、キリストが私たちの罪のために死なれたことと、三日目に復活されたことの二要素でいいのではないか」と思っていたことがありました。そもそも「福音の三要素」という言葉は神学的な用語であって、聖書にそういう言葉が使われているわけではありません。ただ、よく考えると、やはり福音の二要素では不十分で、福音の三要素にする必要があると考えるに至りました。キリストが墓に葬られることは、メシア預言で預言されているためです。イザヤ53:9では、次のように預言されています。
9 彼の墓は、悪者どもとともに、富む者とともに、その死の時に設けられた。…
「彼」というのは、メシアのことです。メシアは墓に葬られると預言されているので、イエスが旧約聖書で預言されていたメシアであると示すためには、墓に葬られるという要素が必要になります。一方、「キリストが弟子たちに現れた」という部分は、メシア預言では預言されていません。そのため、三要素ではなく四要素にする必要性はないと判断することができます。
とはいえ、最も重要なのは、(1)キリストは私たちの罪のために死なれたこと、(2)死から復活されたことの二要素です。ただ、コリントの教会には、キリストが復活したことを信じない人々がいましたし(1コリント15:12)、現代でもキリストは仮死状態から蘇生しただけだと言う人たちがいます。こういう人々に対して、キリストは実際に死んで、復活したのだという点を強調するために、「墓に葬られた」という要素は重要になります。
キリストの埋葬を福音の要素に含めることに関しては、次のような疑問もあります。
なぜ使徒2章や10章のペテロのメッセージではキリストの埋葬のことが語られていないのですか?
使徒2章でペテロがペンテコステの日に語ったメッセージや、使徒10章でペテロが百人隊長コルネリオたちに語ったメッセージでは、キリストの死と復活については語られていますが、埋葬のことについては触れられていません。たとえば、使徒10:39~40では次のように言われています。
39 私たちは、イエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われた、すべてのことの証人です。人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが、 40 神はこの方を三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。
この箇所を見ると、イエスの死と復活については語られていますが、埋葬については言及されていません。最低限信じる必要がある福音の三要素の一つ、「キリストが墓に葬られたこと」がメッセージに含まれていないのはなぜでしょうか。
これは当時の状況を踏まえる必要があります。使徒2章でペテロが語りかけた相手は、エルサレムに巡礼に来ていたユダヤ人です。また、使徒10章で語りかけた相手は、ローマ総督府のあるカイザリヤに住む百人隊長とその家族や知人たちです。つまり、エルサレムでイエスが処刑されて葬られたことや、イエスの墓が空になったことでエルサレム中が大騒ぎになった事実を知らないはずがない人々です。そのため、埋葬の事実に触れる必要がなかったと考えることができます。
一方、当時のコリントの人々や現代に生きる私たちなど、1世紀のユダヤで起こったことを直接知らない人に対しては、キリストの埋葬について触れる必要があります。この違いが、「キリストが墓に葬られた」という要素が使徒2章と8章のメッセージにはなくて、1コリント15章の福音には含まれている理由です。
キリストが神であると信じなくても、福音の三要素を信じれば救われますか?
福音の三要素では、キリストを神として信じる必要があるとは明言されていません。それなら、キリストが神であることを否定していても、福音の三要素を教えていれば救われているのでしょうか。もしそれでも救われると言うのなら、エホバの証人のような異端でも救われていることになります。
答えは「いいえ」です。同じように「キリスト」と言っていても、神でないキリストを宣べ伝える「福音」は「別の福音」であって、聖書の福音ではないためです。パウロは次のように語っています(2コリント11:4、13)。
4 実際、だれかが来て、私たちが宣べ伝えなかった別のイエスを宣べ伝えたり、あるいは、あなたがたが受けたことのない異なる霊や、受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなたがたはよく我慢しています。 …13 こういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。
偽使徒が教える福音では救われません。パウロはガラテヤ1:6~7で次のようにも語っています。
6 私は驚いています。あなたがたが、キリストの恵みによって自分たちを召してくださった方から、このように急に離れて、ほかの福音に移って行くことに。 7 ほかの福音といっても、もう一つ別に福音があるわけではありません。あなたがたを動揺させて、キリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。
ちなみに、キリストが神であることは以下のような聖書箇所からわかります。
(1)ヨハネ1:1~2、14
1 初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。
2 この方は、初めに神とともにおられた。 3 すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。 …
14 ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。
ここで言う「ことば」とは、イエス・キリストのことです。そして、「ことばは神であった」(1節)とはっきりと述べられています。イエスの神性を否定するエホバの証人の『新世界訳聖書(2019年改訂版)』では「言葉は神のようだった」と訳されていますが、誤訳です。ちなみに、その前の版ではしっかりと「言葉は神であった」と訳されています。
(2)ヨハネ10:30
30 わたしと父とは一つです。
イエスは、父なる神とご自分は一つであると宣言しています。これがイエスの神性宣言であることは、この発言を聞いた当時のユダヤ人たちがイエスを石打ちで殺そうとしたことでもわかります(ヨハネ10:31)。ユダヤ人たちは、イエスに次のように言ってます(ヨハネ10:33)。
33 ユダヤ人たちはイエスに答えた。「あなたを石打ちにするのは良いわざのためではなく、冒涜のためだ。あなたは人間でありながら、自分を神としているからだ。」
(3)ヨハネ20:28
28 トマスはイエスに答えた。「私の主、私の神よ。」
十二使徒のトマスはイエスを神と信じていたことがわかる言葉です。また、イエスも、この言葉を聞いて否定したり、神への冒涜だとしてトマスを咎めたりしていません。ご自分が神であることを当然の事実として受け止めています。
キリストが神であることは、コロサイ2:9、ピリピ2:6~7、ヘブル1:3、8、イザヤ9:6などでも確認することができます。
また、新約聖書でキリストは「主」と呼ばれています。原語のギリシャ語では「キュリオス」で、ヘブル語聖書をギリシャ語に訳した『七十人訳聖書』ではヘブル語の「ヤハウェ」の訳語として使われています。つまり、「主」というキリストの呼び名によって、キリストがヤハウェである、神であるという信仰を表明していることになります。
なぜ福音を「三要素」に限定するのですか?
聖書には、救いや福音に関する教えがほかにもたくさんあります。そのうち、なぜ三つだけを取り出すのかと疑問に抱く方がいます。たとえば、次のような救いに関する聖書箇所があるではないかと言います(マタイ7:21)。
21 わたしに向かって『主よ、主よ』と言う者がみな天の御国に入るのではなく、天におられるわたしの父のみこころを行う者が入るのです。
この箇所もそうですが、そういう方は、たいてい救いには行いが必要であるという主張を裏付けるような聖句を引用します。信仰のみで救われるのかという問題については、別の記事で取り上げますので、ここでは置いておきます。
忘れないでいただきたいことは、福音の三要素で救われると語っているのは、使徒パウロであり、聖書(1コリント15:1~5)であるということです。これを否定する人は、聖書が語っていることを受け入れていないことになります。
この点は先述のとおりです。ここで止めてもよいのですが、もう一歩議論を進めて、なぜパウロは1コリント15章で福音の三要素を教えたのかを考えてみましょう。これには以下の4つの理由があると考えられます。
(1)信者が自分の信仰を確認するため
最初の理由は、信者が正しい信仰に立っているか確認できるようにするためです(1コリント15:1)。15章の後半では、コリント教会には復活を信じていなかった人々がいたことがわかります。そのため、パウロはコリントの信者が救いに至る信仰を保っているか確認するように促す必要がありました。
(2)救いの確信を与えるため
イスラム教など、行いによる救いを教える多くの宗教の信者とは違って、クリスチャンは救いの確信を持つことができます(1ヨハネ5:13)。パウロは「この福音によって救われます」と明言することで、信者が自分の信仰を確認し、救いの確信を持てるようにしています。最低限信じる必要がある福音の内容がわかっていないと、救いの確信を持つことが難しくなります。
聖書を完璧に信じている人はおそらくいないのではないかと思います。筆者は30年以上の信仰歴がありますが、今でも聖書を読むと新しい発見がありますし、聖句を勘違いして理解していたと気付かされることがあります。そのため、自分が救われていると確信し、クリスチャンとしての歩みを始めるには、何を信じていれば救われているかがわかる明確な定義が必要です。パウロが提供してくれているのは、そうした信仰の内容の定義です。
(3)教会が救われていない人を見分けるため
福音の三要素によると、キリストの復活を信じていない人は救われていません。そして、そういう人がコリント教会には実際にいたようです。そのため、教会としては、そうした人々に福音に立ち返ることを求め、それに応じないで「別の福音」を語る人々には除名という対応も必要になってきます(テトス3:10)。それは教会が教会であるためにも、本人の救いにも必要なことです。
(4)教会の一致のため
パウロが手紙を書いた当時、コリント教会は分裂の危機にありました(1コリント1:11~13)。この分裂の危機を乗り越えるため、パウロは1コリント1:10で次のように語りかけています。
10 さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって、あなたがたにお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。
この一致を実現するために、パウロはコリント人への手紙で、偶像に献げられた肉、聖餐式、御霊の賜物など、さまざまな問題に対して教会の統一見解となるべき教えを与えています。そして15章では、どのような福音の内容で一致するかを教えていると考えることができます。
実際に、筆者は福音の三要素を基準にして、ある人がクリスチャンであるかどうかを判断しています。もし福音の三要素の一つでも信じていないならば、未信者であって、伝道の対象です。もし三要素をすべて信じているなら、主にある兄弟です。もちろん、キリストと罪をどのように理解しているかも含めてのことです。その場合、聖書解釈に違いがあれば議論を戦わせるかも知れませんが、主にある兄弟として接します。
福音の三要素を批判する人は往々にして、批判をするだけで、何を信じていれば救われているのかがわかるように福音を定義することがありません。福音が定義されていなければ、クリスチャン同士が共通の土台に立って協力することも、救いの確信を持つことも難しくなります。
福音の三要素を「信じる」だけで本当に救われるのですか?
はい。ただ、信じるということは、単なる知的同意ではありません。ハーベスト・タイム・ミニストリーズの中川健一牧師を含め、福音の三要素を信じることで救われると教えている教師、牧師で、単なる知的同意で救われると教えている人を筆者は知りません。福音を信じるという時の「信じる」とはどういうことか、これを論じ始めると長くなりますので、次の記事で解説したいと思います。
> 雑感雑感
福音の三要素を信じることで救われると言うと、欧米では「Easy Believism」と批判されることがあります。日本語に訳すと「安易な信仰主義」となるでしょうか。しかし、福音はシンプルである必要があります。福音は子どももご高齢の方も救われるために信じる必要があるものだからです。ただ、シンプルだからこそ、「それだけでいいのか」と不安になるのも人間です。そのため、さまざまな行いや教えを福音に付け加えようとするのでしょう。
ただ、先述のとおり、福音の三要素は救われるために最低限必要な信仰の内容であり、出発点に過ぎません。信者は義と認められるだけではなく(義認)、キリストに似た成熟した者へと成長していく必要があります(聖化)。この義認と聖化のプロセスを混ぜてしまっているところが、今日の福音理解に混乱が生じている原因ではないでしょうか。
> 脚注脚注
-
コリント人への手紙第一が書かれた時点では新約聖書は完成していない。 ↩