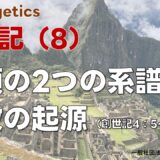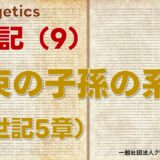死はすべての人に確実に訪れる
米国の政治家、発明家であるベンジャミン・フランクリン(1706年~1790年)は、死について次のような有名な言葉を語っています。
この世の中で確実と言えるものはない。死と税金を除けば。
― Benjamin Franklin
フランクリンが言うように、死はすべての人に確実に、平等に訪れます。聖書でも次のように言われています。
10 私たちの齢は七十年。健やかであっても八十年。そのほとんどは 労苦とわざわいです。瞬く間に時は過ぎ 私たちは飛び去ります。(詩篇90:10)
筆者は人生の折り返し地点を過ぎていますので、人生が「瞬く間」という感覚はわかります。人生七十年、八十年というと、若い人はまだまだ先だと思えるでしょう。しかし、聖書では次のようにも言われています。
14 あなたがたには、明日のことは分かりません。あなたがたのいのちとは、どのようなものでしょうか。あなたがたは、しばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。(ヤコブ4:14)
若いからと言って、七十代、八十代まで生きるという保証はありません。それがこの世の現実であり、聖書が今の世について語っている真理です。
一番大切な終活
日本は今や高齢化社会です。そのため、「終活」という言葉をよく聞くようになりました。終活とは、簡単に言うと「人生の終わりを迎えるにあたっての準備活動」です。最近では、「終活セミナー」というものがあって、エンディングノート(遺言)の書き方から、お墓や葬儀、老後のお金、介護や医療に関する知識まで、さまざまなことを教えてくれるようです。
終活セミナーでも教えてくれないこと
ただ、終活セミナーでも教えてくれないことが一つあります。それは、「人は死んだらどこに行くか」ということです。
しかし、本来、人生の終わりを迎えるにあたって一番大切なのは、死んだ後、自分はどこに行くのかを知ることではないでしょうか。大学受験を受けるのにも何か月、あるいは何年も受験勉強をして準備するのに、人生で最大の試練とも言える死を迎えるにあたって、死後のことを何も知らないまま臨むというのは、どう考えてもバランスを欠いています。しかし、たいていの人は、「死後、自分がどこに行くのかを知る」という一番大切な終活をすることなく、死を迎えてしまうのです。
死後観が生き方を決める
死後の世界のことを考えることは、死んだ後だけではなく、生きている間にも重要なことです。それは、人は死んだらどこへ行くかという死後観が、人が今をどう生きるかという日々の決定を左右するためです。ニューヨークのリディーマー長老教会の牧師であるティモシー・ケラー(1950年~2023年)は、次のように語っています。
今あなたがどう生きるかは、あなたが将来について何を信じているかによってすべて決まってくる。
― Tim Keller, “The New Heaven and New Earth” (podcast of sermon, Redeemer Presbyterian Church, April 12, 2009), http://podbay.fm/show/352660924/e/1317415673.
また、ケンブリッジ大学教授で、小説『ナルニア国物語』の作者であるC・S・ルイス(1898年~1963年)も、次のように語っています。
歴史を読めばわかることだが、現世で最も大きな働きをしたクリスチャンは、来世のことを最も深く考えていた人々であった。ローマ帝国を改宗へと導く礎(いしずえ)となった使徒たち自身や、中世を築き上げた偉大な人々、奴隷貿易を廃止した英国の福音派たちが地上に足跡を残せたのは、彼らの思いが天に向けられていたからにほかならない。
― C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1960), p.104.
ルイスが言うように、この世界を良くしたいのであれば、また良い人生を送りたいのであれば、健全な死後観を持つことが重要です。この死後観は、人生の方向性を決める世界観につながっているのです。
「今だけ、金だけ、自分だけ」という生き方の背景にある世界観
現代を生きる人々を方向付けている世界観は、聖書が語るような死後観ではなく、ジョン・レノンが「Imagine」で歌った死後観であるように思います。「Imagine」の歌詞は、次のような内容です。
Imagine there’s no heaven(想像してごらん、天国なんてないんだ)
It’s easy if you try(やろうと思えば簡単さ)
No hell below us(僕らの下に地獄はなく)
Above us only sky(僕らの上には空だけがある)
Imagine all the people living for today(想像してごらん、人々が今日のために生きている姿を)
ここでジョン・レノンは「天国なんてない」「僕らの下に地獄はない」と歌っています。死後の世界はない、「死んだら終わり、無に帰るだけ」という死後観です。
「想像してごらん、人々が今日のために生きている姿を」と言うと聞こえはいいですが、「Imagine」の世界観は、今が良ければそれでいい、という刹那的な生き方につながります。また、死ねばすべて無になるという世界観は、多くの現代人が抱えている「虚無感」にもつながっています。どのように生きても結局は死んで無に帰るのだから、人生に究極的な生きる意味はないと空しさを感じてしまうのです。その結果、行き着く先は「今だけ、金だけ、自分だけ」という自己中心的な生き方です。このような人生観のむなしさは聖書でも語られていて、次のように言われています。
3 日の下で行われることすべてのうちで最も悪いことは、同じ結末がすべての人に臨むということ。そのうえ、人の子らの心が悪に満ち、生きている間は彼らの心に狂気があり、その後で死人のところに行くということだ。(伝道者の書9:3)
ここで言う「同じ結末」というのは、言うまでもなく死のことです。良い生き方をしても悪い生き方をしても等しく死に、同じ結末を迎えるのであれば、「人の心が悪に満ち」て、「心に狂気」を抱えて生きることになるのも不思議ではありません。
ただ、「死んだら終わり、無に帰るだけ」という世界観は、死を経験したことのない人間の想像の産物でしかありません。ジョン・レノンも「想像してごらん」と言っているように、死後の世界を実際に知っていて、この詩を書いているわけではないのです。
死後の世界を知ることができる唯一の情報源「聖書」
死後の世界について最も信頼できる情報源は、聖書です。それは次のような理由によります。
1)聖書の神は、人を造ったメーカー
聖書は、創造主である神が人を創造したと宣言しています(創世記1:27)。このように宣言し、創造の過程を理路整然と書いている書は、世界広しと言えども聖書しかありません。
製品の仕様を調べる時は、メーカーが提供している情報を調べます。たとえば、スマホのバッテリーにどれくらいの寿命があるのかを知りたかったら、メーカーのWebサイトを見ます。また、製品が寿命を終えてリサイクルに回す場合は、どのようなリサイクル方法があるのか、メーカーが提供する情報を見ます。
それと同じで、人間が死後どこに行くかも、人間とこの世界を創造した神から情報を得る必要があります。天国や地獄があるのであれば、それも天地創造の神が造ったものです。そのため、死後の世界のことは世界の創造主にたずねるほかありません。
2)死からよみがえり、今も生きておられる唯一の方、イエス・キリスト
聖書が死後の世界を知る唯一の情報源であるというもう一つの理由は、死後の世界を説くあらゆる宗教の創始者の中でも、死からよみがえった方はイエス・キリストしかいないためです。イスラム教も、仏教も、創始者はすべて死に、墓に葬られたままです。しかし、キリストは実際に死を体験し、復活し、今も生きておられる唯一の方です。ほかの宗教家も、自分は死を体験し、現世に戻ってきたという主張をすることがあります。しかし、いずれも客観的な証拠に欠ける上に、結局は死んで葬られ、墓にとどまったままです。そのため、死後の世界について語る権威があるのは、キリストについて教えている聖書しかありません。
キリストの復活は事実であると歴史的に立証するための根拠は十分あります。そのような根拠の一つが、キリストは復活したと宣べ伝えた弟子たちが、ローマ帝国の死の脅迫や迫害にも屈せず、殉教していったことです。人は、嘘だとわかっている主張のために死ぬことはできません。
NOTE:キリストの復活が歴史的事実かどうかの検証については、中川健一「人生の謎を解く(5)―復活は歴史的事実か―」(https://seishonyumon.com/audio/676/) が参考になります。ぜひお聞きください。
聖書は、人が死後の世界を知ることができる唯一の光です。この光で照らすことなしに、生きている間に死後の世界について知ることは不可能です。
聖書が語る「死」
さだまさしが作詞、作曲した曲に「防人の詩」というものがあります。日露戦争を舞台にした映画「二百三高地」のテーマ曲にもなった歌です。歌詞は次のとおりです。
おしえてください
この世に生きとし生けるものの
すべての生命に限りがあるのならば
海は死にますか 山は死にますか
風はどうですか 空もそうですか
おしえてください私は時折 苦しみについて考えます
誰もが等しく 抱いた悲しみについて
生きる苦しみと 老いてゆく悲しみと
病いの苦しみと 死にゆく悲しみと
現在(いま)の自分と答えてください
この世のありとあらゆるものの
すべての生命に 約束があるのなら
春は死にますか 秋は死にますか
夏が去る様に 冬が来る様に
みんな逝くのですか
出典:「防人の詩/さだまさし(3333 in 武道館)」(さだまさしオフィシャルYouTubeチャンネル)
実際には「みんな逝く」(人はすべて死ぬ)のですが、この詩では死に対する強烈な「違和感」が表現されています。なぜ人は死ぬのですか、という根本的な問いです。「そんなことは当たり前じゃないか」と思われる人もいるでしょうが、人が生まれて死んでいくのが自然の理であれば、なぜ人は死に対してこのような強い違和感を抱くのでしょうか。親しい人が死んだ時、どうして人は悲しみに打ちひしがれるのでしょうか。どうして人は死ぬことに恐れを感じるのでしょうか。
それは、死というものが、本来はこの世界になかった「異物」だからです。さだまさしが歌った死に対する違和感は、ここから来ています。そしてこの違和感は、聖書の世界観に通じているのです。
神が創造した初めの世界に「死」はなかった
聖書の初めの書、創世記には、神が創造した初めの世界に死はなかったと記されています(創世記2:17、3:22)。聖書的には、「死」とは本来この世界には存在しなかったものなのです。
死は、最初の人類、アダムとエバの罪を通して世に入っきたものです。使徒パウロが言うように、「一人の人(※アダム)によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして、すべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がった」のです(ローマ5:12)。
聖書を通して死後の世界を知ろうとするとき、本来「死」はなかったということを起点として考える必要があります。そうでないと、聖書が語っていることの意味を汲み取ることが難しくなります。
死とは分離
死について聖書が教えているもう一つのことは、死とは消滅を意味するのではなく、「分離」を意味するということです。人が死ぬと土に帰ってなくなるのではなく、魂と体が分離して、体は朽ちても魂は生き続けるということです。この魂が行く所が、聖書が語る死後の世界ということになります。
聖書が語る死後の世界
霊魂は不滅
聖書は霊魂の不滅を教えています。死ぬと体と魂が分離して、魂が生き続けるということはそういうことです。
このことは、世間一般の感覚とも通じています。人間は、基本的に霊魂の不滅を信じています。たとえば、先祖供養をするのは、先祖の魂が今も生き続けていると信じているためです。また、死者の世界と生者の世界を分かつ「三途の川」という概念も、人は死んでも魂は生き続けるという思想を反映しています。
このような考え方は、聖書のことばとも一致しています。伝道者の書3:11では、次のように言われています。
11 神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が行うみわざの始まりから終わりまでを見極めることができない。
「人の心に永遠を与えられた」とは、「人は永遠を思う心を与えられた」とも、「人の心(魂)が永遠に生きるようにされた」とも読むことができる言葉です。いずれにせよ、体は朽ちても魂は死者の世界で永遠に生き続けるという思いは、神から与えられたものです。
死後のさばき
聖書の中心的な教えの一つは、人は死後にさばきを受けるというものです。聖書では次のように言われています。
人間には、一度死ぬことと死後にさばきを受けることが定まっている(ヘブル9:27)
人は、死後に神のさばきを受けるので、そのことを前提に生きよというのが聖書のメッセージです。また、この聖句は、輪廻転生はないというキリスト教の教えの根拠にもなっています。この聖句では人は「一度死ぬ」と言われているので、輪廻して何度も死ぬことはないことも言外に語っているためです。つまり、人生は一度限りのチャンスで、死んでからやり直すことはできないということです。
死者の復活
もう一つ新旧約聖書を通して教えられていることは、死者がいつか必ず復活することです。旧約聖書のダニエル書では次のように言われています。
2 ちりの大地の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠のいのちに、ある者は恥辱と、永遠の嫌悪に。(ダニエル12:2)
新約聖書のヨハネの福音書でも、イエス・キリストは次のように語っています。
28 このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみな、子の声を聞く時が来るのです。 29 そのとき、善を行った者はよみがえっていのちを受けるために、悪を行った者はよみがえってさばきを受けるために出て来ます。(ヨハネ5:28~29)
善人も悪人も、死後によみがえるというのが、聖書の一貫した教えです。善人は永遠のいのちを受け継ぐために、悪人はさばきを受けるためによみがえるのです。そして、このさばきによって、人が死後の世界をどう永遠に過ごすかが決まります。
聖書は死後に人がどこに行くかを教えている
聖書は、人が死後にどこに行くかを明確に教えています。
ただ、死後の世界に関する聖書の教えが、教会で教えられることが少なくなっているのも事実です。そのため、クリスチャンであっても、死後の世界のことを正確に知らない人が多いのではないかと思います。そして、それが現代の教会に力がなくなっている原因の一つではないかとも思います。C・S・ルイスは、先ほど引用した言葉に続けて、次のように語っています。
クリスチャンがあの世のことに思いを馳せることが基本的になくなって以来、現世での働きがあまりにも非力になってしまっている。天を目指せば、地は「おまけ」として与えられる。地を目指せば、天も地も得られない。これは奇妙な法則のように思えるが、同じような法則は別の領域でも働いていることを見ることができる。
― C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Macmillan, 1960), p.104.
このルイスの言葉は、永遠のいのちを与える福音よりも、今ある社会の改革を重視する「社会福音(Social Gospel)」を受け入れてきた今のキリスト教に、そのまま当てはまるのではないでしょうか。
以上のような視点に立って、このメルマガでは、これから何回かにわたって聖書が語る死後の世界について解説していく予定です。
最後に
今生きているすべての人にとって、死は未知の領域です。
人は未知のものを恐れます。そのため、たいていの人は死という現実に目をそむけて生きています。そして、死という現実をできるだけ先延ばしにしようと懸命になっています。健康に気遣うこと自体はすばらしいことですが、それだけでは「地を目指せば、天も地も得られない」というルイスの言葉どおりの人生になってしまいます。
しかし、聖書が教える死後の世界を知れば、今を生きるための方向性も見えてきます。そして、聖書の真理を知っていくと、死に対する恐れも徐々に取り去られていきます。死後の世界と、死後まみえることになる創造主なる神がどのような方であるかがわかってくるためです。
聖書では、真理を求め、真理を知る人に次のような約束が与えられています。
32 あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にします。(ヨハネ8:32)
また、イエス・キリストは次のように宣言しています。
6 イエスは彼に言われた。「わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。わたしを通してでなければ、だれも父のみもとに行くことはできません」(ヨハネ14:6)
死後の世界について、聖書が教える真理をご一緒に探っていきましょう。